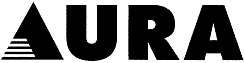音楽院に掲載しておりました谷川英勢講師による7月8日開催の藤井眞吾氏マスタークラスのレポートを転載します。

アウラ音楽院 2012.7.8(日)
藤井氏のマスタークラスの様子をお伝えしたいと思います。
藤井氏のレッスンの特徴は、ギタリストとしてだけではなく、指揮者や作曲家目線で音楽を大きな規模でとらえ的確にアドバイスしていくところ。
受講生1人目、土谷有希さん / 受講曲:鐘の響き(ペルナンブーコ)

トップバッターということもあり、やや緊張している様子で弾きはじめる。
一通り演奏を聴き終わり「ありがとう、とってもよかったよ!」と和やかな口調でレッスンが始まる。
・どこがメロディーか?
まず最初に、「この曲のメロディーはどこですか?」と尋ねる。メロディーとその他の音(内声、ベース)のバランスを考えて、なおかつメロディーはレガートで綺麗に弾くことが望ましい。メロディーの弦が(2弦から1弦などに)変わる際も、音色を統一できるよう心掛ける。聴き手側にも「今の音はなんだろう?」と思わせないように、大げさなくらい明確に旋律を示す。なんとなく弾くと演奏のバランスもなんとなくになってしまう。
・右手のコントロール
指をどう使うか。例えばメロディーを弾く指がi・mである場合の基礎練習としては、2弦の開放弦をi・mで交互に弾きクレッシェンド、デクレッシェンドを滑らかに弾く練習をする。この時に突然大きな音が出たりしないようi・mのバランスに注意をはらう。
次に和音を弾く場合のテクニック。p・i・m・aを1・2・3・5弦などに置いて全部同時に弾弦して、特定の指の音(例えばm)だけ他より大きく弾く練習をすることによって曲を弾いた際の右手のコントロールができるようになる。
音量のメカニズムについて。ギターの音量はどれだけ表面板が振動するかが大きく関わっている。弦の弾き方は、右指が弦にタッチした時点から弦を下(ボディ側)に押し込み弾弦すること。すなわちこの”押す力”が音量に完全に比例するとのこと。爪で横に引っ掻きあげると音質も軽く、音量にも貢献しない。
これらのことは言われてすぐに出来るようになることばかりではないので、やはり普段からの練習に上手く取り入れていく必要があると感じた。
受講生2人目、西村拓也さん / 受講曲:ダンサ・ポンポーサ(タンスマン)/エチュード1番(レゴンディ)

難曲であるタンスマンの曲を堂々と演奏。
・版を選ぶということ
まずはじめに、この曲はアレクサンドル・タンスマンがアンドレス・セゴビアの為に書いた曲で。この曲だけではなく我々ギタリストのレパートリーの中にはセゴビアの為に書かれた曲が数多く存在する。例えば、ポンセやタンスマン、テデスコ、トローバ…等。これらの作曲家に共通したのは全員ギターが弾けなかったということ。では何故ギターの作品を書けたかというと、やはりそこにはセゴビアとの綿密なやり取りがあったことがうかがえる。
セゴビアがなくなって数十年たった今、セゴビアの遺品の中から作曲家の書いたマニュスクリプトなどが発見され、BERBENからセゴビア・アーカイブとして出版されているし、セゴビアが手をつけなかったものや未出版だったものもジラルディーノという音楽学者が出版している。そこで我々が注意しなければならないのが、原典版とセゴビア版とを比較して「セゴビアは間違って弾いてたんだ、原典版の方が正しいからこっちで弾こう!」などと安直なことを考えてはダメだということ。それは、ギターが弾けない作曲家達にとってセゴビアなどのギタリストのアドバイス・協力はなくてはならないものだったからである。
・アーティキュレーションはそろえる!
例えばこのタンスマンの曲の後半29小節から低音のメロディーがはじまるが、そこをあまり切り(スタッカート)すぎると、メロディーとしてとらえづらくなるし、その少し後にもう一つの声部が追いかけて入ってくる所があり、そこでも上のメロディーは同じ音型が繰り返される。そうなると急にテクニック的に難しくなり、最初は切っていたメロディーが2声になると(制御できなくなり)伸びてしまうなどということがある。やはり各声部ごとに考えると、同じ音型ではアーティキュレーションがそろってないと不自然さは拭いきれない。もちろんギターという楽器でそれを実行することは容易ではないが、普段からの練習でこの緻密な作業に対していかに考え取り組んでいるかが重要なのだと思われる。
受講生3人目、小林真紀さん / 受講曲:月光(ソル)
・緊張対策はどうやっている?
「どんな人でも人前で演奏するときは緊張して手が震えたりします。緊張はして当たり前なんです・・・」さらに続けて「緊張を防ぐことはできませんが、対策は立てられます」と藤井氏。
では対策とは何か?
それは例えば右手が弦に触れずに浮いている状態になると手が震えだす。必ずどこかの弦に指を置いておく必要がある。それはつまり、立っているときに壁に手をついてもたれかかり体を安定させている状態に近く、体が落ち着くと気持ちも落ち着くという理論である。なので右手の指は 必ず”次”を考えながらなるべくどこかの弦の上に置くという作業が必要になる。例えば、低音の5弦をpの指で弾いてその次にpで弾く弦が6弦だった場合、最初の5弦を弾いた直後にpは6弦に置いておく。そうすれば必ずpの指はどこかに置いている状態になるうえに”次”に弾く弦に置いておくことによって直ぐにその弦を弾くことができるという、まさに「安定」と「次の準備」が同時に得られる理想形ができるのである。
さらに、緊張すると大抵の人が呼吸が浅くなる。それは肺の下にある横隔膜が緊張によって縮こまり動く幅が狭くなっているから。そういった時の対処法としては、息をたっぷり吸ったあと口を細くして「スゥー」と息を(できるだけ)長く吐き続ける。これを約3回ほど繰り返すと、だんだん体が落ち着いてきて結果気持ちも落ち着いてくるとのこと。
・爪に対する意識
弦を弾く際に、最初にあたる部分の爪が長すぎると引っかかりの原因になるので注意する。爪が引っかかってしまうと手は掻き上げるしかなくなるので、引っかけた音しか出ず、そうなると前述で述べたとおりギターの表面板に振動は伝わらず軽い音になってしまう。クラシックギターでいうところの”爪”とは、いわゆるエレキギターなどの”ピック”の替わりというわけではないということ。ではなぜ爪を使うかというと、指の肉の部分で弾くより音色に変化が付けやすく幅もでるということから爪が主流になってきた。
爪の削り方に関しては、文章で説明するのは至難の技なのでここでは割愛させていただく。詳しく知りたい方は、この日藤井氏からも紹介があったがギタリストのスコット・テナントのギター教則本【パンピング・ナイロン】を参考にされると良いかと思われる。図を用いて丁寧に説明してくれているので、非常に分かりやすく有難い。
受講生4人目、山本大河さん /受講曲:ハンガリー幻想曲(メルツ)

まだ14歳とかなり若いが、素晴らしい音楽性と技術でハンガリー幻想曲をらくらく弾きこなしていた。
演奏が終わり藤井氏が「素晴らしい、ありがとう!」「ところで今いくつ?」の問いに受講生は「14歳です、でも今月の28日に15歳になります」すると藤井氏は「7月28日?おめでとう!!それはバッハの命日だよ、君はもしかするとバッハの生まれ変わりかもしれない(笑)」と言って、会場の笑いを誘っていた。
・楽譜を読み取る能力
「君はこれから凄くのびていくと思うよ。でも本当に大事なのは技術的なことではなくて、音楽を理解すること」つまりは楽譜から色んな情報を読み取る能力を養うことが重要になってくるという。受講曲でいうと、一般的には後半のテクニックを駆使した華やかな所に目が行きがちだが、むしろ冒頭のゆったりとした部分にこそ音楽の大切な要素が詰まっていると指摘する。そして受講生に対しいくつか質問をなげかける。
「最初に書いてあるMaestosoってどういう意味?」
「堂々と、という意味です」
「そうだね、ではこの曲は何分の何拍子?」
「4分の4拍子です」
「うん、じゃあその堂々とした4分の4拍子を振ってみよう」といい受講生に指揮を振らせ、それに合わせて藤井氏が自らギターで冒頭を弾いてみせる。
「どう?大河君はさっきまでどうやって弾いてたか覚えてる?」「君はさっきまで8分音符で音楽を追っていたよね?」つまり、4分の4のところを8分の8という音のとらえ方で演奏していたことになる。そうなるとそもそものリズムの感じ方が大幅に変わってくる。譜面を見るよりも先に他のギタリストの演奏などを聴いてその曲を認識してしまうとこういった状態に陥りがちなので、譜読みする際はなるべく先入観を持たずに譜面から忠実に情報を読み取ることが大切といえる。
・ピッチ(音程)の調整
ギターという楽器は正しい音程を保って演奏するのが非常に難しい楽器である。例えば受講曲でいうと2小節目の「ミ・レ・ミ・レ・レ~」や(似た個所で)4小節目の「ミ・レ・ミ・ミ・ミ~」などの4弦でハイポジションまで使って弾くところなどは特に気をつけたい。ギターにとって3,4弦あたりのハイポジションは最も音程が狂いやすい場所なので、そういった問題を解決するにはビブラートが重要になってくるという。どういうことかというと、(ハイポジションに限らないが)音を出した瞬間にもし音程が少し狂っていたとしてもビブラートをすぐにかければ狂っているようには聴こえなくなる。こうしたテクニックを駆使して常に正しい音程になるよう微調整していかなくてはならないのだという。
受講生5人目、鈴木雅幸さん / 受講曲:ソナチネ(モレル)

この曲は”デビッド・ラッセルに捧げる”として書かれた曲であるが、藤井氏はかつてデビッド・ラッセルに師事しており、さらにこの曲の作曲者であるホルヘ・モレル本人の指導をも受けたことがあるという。なので、普段はなかなか耳にすることのない貴重な話も聞くことができた。
まず、6弦チューニングに関するアイディアとして、通常は1楽章→2楽章→3楽章は6弦D→E→Dとなるが、そうするとせっかく良い雰囲気で曲を弾いていても曲間のチューニングでその雰囲気が台無しになってしまうので、工夫して全楽章をDで演奏することを勧めていた。
・アクセントの位置
「もう少しアクセントがほしいなぁ」とアクセントについて指摘する。冒頭3小節目4拍目などのいわゆる”ぶつかっている音”などにはアクセントをつける。スラーがかかっている所にも注意しなくてはならない。この場合のスラーというのはアクセントに深く関わっていて、スラーを普通に弾くとスラーがかかっている方の音にはアクセントが付きその後の音は自然に弱くなる。つまりスラーを上手く使うことによって自動的にアクセントが”生きてくる”ということになるのだという。
続いて藤井氏は速度記号の解釈などに話を移す。受講曲の6ページ目(88小節目あたり)から”Lento espressivo”という指示がある、しかしデビッド・ラッセルは遅くせずに逆に速く弾いているのだという。なぜかというと、5ページ目(60小節目)から”Meno tempo”という指示がでており、そこからさらに86小節目でrit.して先ほどの88小節目に入ると”Lento”では遅くなりすぎて退屈な感じがでてしまうので、逆の発想で速く弾いてみたのだという。デビッド・ラッセル本人が言っていたとされる話によると「音楽の仕組みの中でテンポの変化やダイナミクスの変化などのことを考えると、私はこの部分はLentoせずにもっと速く弾いた方が良いと思うし、本来の演奏効果も十分得られる」などと話していたのだという、さらにその旨をホルヘ・モレルに提案したところ「その解釈でも良いと思う」と同意を得たのだという。しかし藤井氏が本来言わんとすることは、決して”この部分は速く弾かなくてはならない”という訳ではなく、作曲家が狙っていた演奏効果が時と場合によっては逆の方法でも成立する可能性がありうるということで、そういったアイディアを常に持っていることが大切なのだということである。
・ダイナミクスの解釈について
受講生からの質問で「原典版とではダイナミクスが大きく変わっていますが、どう解釈すれば良いですか?」それに対して藤井氏は「私も曲を書くので、その曲を演奏するアンサンブルなどを指導することもあります。その時にピアノやフォルテの音量について聞かれます」その際によくある質問というのが「先生、ここはピアノと書いていますがどれぐらい小さく弾けば良いのでしょうか?」などといったこと。しかし、音楽の場合ピアノやフォルテに絶対的な音量は決まっておらず、必ずその前後との相対的なもので決まるので解釈を間違ってはいけないのだという。そもそも曲の原典版といえど、我々のもとに届くまでにいくつかのプロセスを経てきているわけだから、一体どういった環境で出版されたのか?最初に出されたものが本当に作曲家が言いたかったことなのか?そういったことも考慮しながら曲に取り組みたい。
受講生6人目、佐々木宣博さん / 受講曲:ソナタ・ロマンティカより第1楽章(ポンセ)

・ソナタ形式
ギターの作品でソナタ形式のものは数少ないが、その中でもこの「ソナタ・ロマンティカ」などは素晴らしいソナタの構図をもっているという。そこで藤井氏から受講生に質問
「ソナタ形式ってどんなもの?」
「提示部、展開部、再現部、そしてコーダ(結尾部)から構成される形式です」
「うん、では佐々木君はこの曲でどこが一番グッとくる?」
「戻ってきた(再現)ときです」
「そうだね、僕もそうなんだよ!」といい、ソナタについて説明する。
そういったいわゆる「グッとくる」再現部を作るには、その前の提示部などのキャラクターなども一つ一つはっきり意思を持ってドラマを作っていかなければならない。そこをなんとなく弾いていると感動的な再現部にはならず、いつの間にか戻っていた..などということになってしまう。そうなってしまうことを避けるために必ず各部を大切に考えて、全体のストーリーを創り上げていくことが重要なのだという。
・テンポは正確に
そもそも指示も無いのにテンポを揺らしすぎるのは良くない、a tempoなどの指示がある際は必ず正確に”もとのテンポ”に戻すこと。もとのテンポといっても意外と難しく、いわゆる”もとのテンポのつもり”では駄目なのである。なので、最初のテンポを体に覚えこませてa tempoがきたらそこに正確に戻す訓練が必要になる。
さらに、転調する時にもテンポ感が重要になってくる。転調する時にテンポまで大きく変えてしまうと、聴き手側には一体何が起こったのかが分からなくなる。テンポをしっかりもとの速さに戻すことによって、シンプルになり転調したことが際立つのだという。
この他にも、曲の背景や作曲家の話、指揮についてなど、いくつか断片的に話題にあがったが、限られた時間の中ではそれらの全てを聞くことはできなかった。しかし藤井氏本人も「また次の機会を作って皆さん一緒に勉強しましょう!」と仰っていたので、また次回のマスタークラスが楽しみである。

今回のマスタークラスは聴講生にも受講曲の譜面が配布されるなどの配慮もあり、受講生はもちろんのこと聴講生側もよりいっそう充実したマスタークラスになったように思う。
最後に、藤井氏と今回のマスタークラスの発案者である益田氏による2人のミニコンサートで締めくくられた。
谷川 英勢