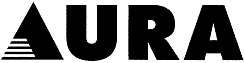ギターの変遷、音の成り立ち
最近はギターやギターの歴史に関する書籍も充実していますし、ネットもあるので知ろうと思えばかなり詳しく調べることができます。
ここでは製作する立場から、ギターの歴史をもう一度たどり、思いついたことを書こうかと思います。
本当のところは分かりませんが、歴史を眺めると色々な意味が見えてきます。
答えはひとつではないので、後から訂正するかもしれない思いつきも書いておきます。
ギターは1800年前後で5コース、6コースの複弦から、6本の単弦に移っていきます。
ギターは旋律楽器ではなく、ハーモニーやベース音を出せ、一人で複雑な音楽を構築できます。
譜面の音を聞き手に伝えるには、一つ一つの音がクリアーである必要があります。
それに適当な空間があれば心地よく音楽を聴けます。当時流行りのギターを人前で弾くことも多くあったろうし、教則本でも単弦を薦めているものもあります。
アグアドはフアン・ムュノアに6単弦ギター製作のアドバイスもしています。結果として、人々が単弦の音を好むようになっていきました。
グラナダの中心にカテドラルがあります。
1500年代前半に作られた建物は今も現役で使われているようで、自由に出入りできました。
硬い木のベンチに座るとパイプオルガンの単音が長く短く聞こえました。
どうやらオルガンの修理か調整のようでしたが、意味のない単音でも、今にも音楽が始まりそうな圧倒的な音色でした。
ゴシック様式の凸凹の壁や、ほの暗い高い天井で乱反射した音は体を包み込むようで、音源がどこだか分かりません。
何処からか聞こえてくる音楽に身を包まれるような感覚は、天上の音楽にふさわしく、教会音楽には最適の空間だと思いました。
オルガンの単音が持っている倍音はひとつの和音のようで、反射して遅れて聞こえる音は心地よい残響を生み出します。
リュートや1700年代のバロックギターなどで見られる複弦、多弦は教会の空間が作る音を模倣しようとしていたのかも知れません。複弦は立ち上がりのアタック音が僅かにずれ、遅れて聞こえる反射音のようです。
また複弦を開放で同じ音に合せ、ハイポジションで押さえても、同じ音高になるほどの弦の精度はなく、僅かに濁ります。この濁りも暖かな音色に聞こえます。多弦になればなるほど、弾いてない弦の共鳴音が多くなり、教会の残響のようです。
模倣が目的ではないのでしょうが、バロックギターの立体的なロゼッタも教会の天井の様に見えてきます。
小さな部屋で、こうした複雑な響きをもつ楽器は心地よく聞こえますが、大きな空間で聞けば、空間が作る反射音で響きすぎ、音楽がよく聞き取れません。
音楽ホールでは人間の話し言葉がよく聞き取れないのと同じで、響きが多い空間ではクリアーな音源ほど聞き取りやすいです。
19世紀ギターとその変遷
古典派からロマン派に移り変わる時期、ギターの作曲家が多く表れます。
カルリ(1770~1841)、ソル(1778~1839)、ジュリアーニ(1780~1840)、アグアド(1784~1849)、レニャーニ(1790~1877)、カルカッシ(1792~1877)、メルツ(1806~1856)、コスト(1806~1883)などギターリストにとって重要な人たちです。
1800年前後はパリを中心とした北ヨーロッパでギターブームでしたが、製作の方でも色々な試行錯誤があり、より良いと思われる改良が入り乱れています。
ギターブームにより、少しずつよその国の事情も知り、需要が増え、製作家も増えますが、何がいいギターか良くわからない時代でもあったと思います。
弦の数が5複弦、6複弦、6単弦、と変化していきますが時代や地域で形態が違います。
また、それまで駒は、弦を穴に通して結ぶだけでしたが、この時期に今のようなサドルが使われ始めました。
サドルは金属のフレットを利用したものや、駒の縁を利用したもの、ヴァイオリンのようなタイプなど、他にも色々表れます。
また小さな木ペグを利用し、いまのスチール弦ギターのピンブリッジと同じ構造のものが発案され、サドルとの組み合わせで幾つものパターンになります。
今の糸巻きで使われている機械式の糸巻きが発明されたのもこの時期(1820年頃)です。面白いのはエレキギターのように横にペグが出ているタイプも作られています。
最近Wホールの駒をよく見かけますが流行なのかもしれません。Wホールは、普通の結び方も出来、音色の違いも確認できます。
ロマニリョスのオリジナルで3穴のタイプもあります。Wホールのアイデアは最近のものだと思われがちですが1800年前半には生まれていました。
当時は、複弦から単弦に主流が移る時期ですから、ギターを買い換えないで、6複弦のギターに6本の弦を張って使っていた人も多かったはずです。
誰かが余った穴を利用して新しい弦の結び方を試したのだと思います。
ナットを取替え、糸巻きの木ペグと弦の数が合わないのではなく、ちゃんとWホールを意識したものが作られています。
使用者や製作家の間では、「複弦より単弦だよね」、「機械式は調弦が楽だよ」、「このサドルだと弦高調整が出来るよ」と、目新しいギターの品評にうるさかったろうし、「こっちのほうが合理的だ」、「音色のためにはこれだ」と新しい音作りに熱中している製作家も想像できます。
もちろん伝統にこだわった製作家もいたはずですが、なんとも楽しそうな時代です。
1700年頃、ストラディバリウス達が作っていたガット弦のヴァイオリンは本来バロックヴァイオリンと呼ばれる楽器でした。
しかし1800年前半にモダンヴァイオリンに改良(改造)されます。
弦長を長く、棹の仕込み角を大きく、力木を丈夫に直します。これらの改良はスチ-ル弦の張力に耐えるようにし、力強い音色で音量を増大させるのが主な目的でした。
音楽家が次第に宮廷への依存から離れ、ベートーヴェン(1770~1827)がコンサート形式で生計を立てられるようになった時期ですが、大ホールでの音量が求められていたからです。
しかもヨーロッパの楽器商達によって、殆どのバロックヴァイオリンがモダンヴァイオリンに改良されます。
ちなみにガット弦に金属細線を巻いた低音用の巻線は1660年には作られているので、バロックヴァイオリンでも使われていたと思われます。
金属弦の歴史は古く15世紀頃にはあったようです。チェンバロには金属弦(真鍮)が使用されているし、ピアノ用の太い巻弦が開発されたのは1800年の初めです。
1800年頃のギターはガット弦が使われていたと言われていますが、新しい試みが入り乱れた時代ですから、流行りの金属弦を使用したギターもあったような気がします。
ピンブリッチは縛りにくい金属弦の為かもしれないし、フレットを利用したサドルや0フレットも金属弦による磨耗を防ぐ為かもしれません。
シュタウファー(ドイツ)の弟子のマーチンは1833年渡米し、その後のフォークギターの発展に大きな影響をあたえます。今のフォークギターの原型が生まれた時代ですから、類似した形からの連想でしかないのかもしれません。
弦は消耗品ですから確認できませんが、この頃にはガット弦からスチール弦への移行が始まっていたのではと思います。
ガット弦用のギターにスチール弦を張りギターを壊してしまったと推定される19世紀ギターが多いと聞きました。
順反りや表板の落ち込みの原因と考えているのだと思いますが、ガット弦のままでも同じトラブルは多く、ギターの宿命ですね。
北ヨーロッパのギターブームは徐々に衰退していきますが、1900年始め頃にはスチール弦の方が多かったのではないかと思います。
今ラコート(フランス)が手元にあります。ラベルがはっきり読めませんが1820年代だと思われます。
二重に貼った指板や駒交換、表板の割れの補強など修理の手が入っていますが、大きなダメージはなくそのまま弾ける状態です。
200年近く経って、今でも音が出せるのはかなり幸運な楽器です。それは修理をしながら大切に扱われたからだと思います。木工製品ですから、ただ大切にしていても200年は持ちません。
修理の役割は大きいと思います。出来た当時の音は、はっきりとはわかりません。
ガット弦でないし、当時の奏法が指弾きか爪弾きかも良くわかりません。少なくとも二回は裏板を剥がしてあるし、駒交換や割れの修理で表板の厚みも減っているはずです。
そして何よりも、当時として出来のいい楽器だったのかどうかもわかりません。
でも弾くと当時の音や雰囲気を想像できます。1800年始のギターブームでは、耳もとで音が大きくうるさいヴァイオリンより貴婦人達には人気があったようです。
ギターに人気が集まったのは、リュートより調弦が楽だったし、ピアノより手軽だし、ソルはかっこよかったろうし…等色々な理由が想像できます。
先日パノルモ(イギリス)を弾く機会がありました。
1849年のスパニッシュスタイルで、大きな故障や修理はなく、とてもいい状態でした。
サドルがなく駒の木を利用している為か、甘く、鈍い音ですが、音色はラコートよりトーレスに近く、力木は7本バーです。ラベルに書いてあるようにスペイン的な音色です。
パノルモはソルとの出会いをきっかけに、パヘスなどのスペイン的な工法の影響をうけ、一本棹やペオネスを使って作られています。
ラベルに書いてある「スパニッシュスタイル」はこの工法のことか、7本バーのことかはっきりしませんが、ひょっとしてガット弦用に軟らかく作られたギターのことかもしれません。
ボディーサイズを大きくしてサドルを使えば無理なくトーレスの音につながるイメージが出来ます。
パノルモを弾いていた当時の演奏家にとって、トーレスの音は斬新で驚異的だったと思います。
でもトーレスからパノルモを見ると無理なくつながるのは面白いですね。同じつながりで思いつくのはブーシェです。
後期のブーシェの音の特徴は、重たく変化していくオルガン的な立ち上がりの低音と、ラコートのような古典的な雰囲気の音質です。
ラコートと弾き比べると、後期のブーシェの音は現代版ラコートという気がします。
前期のブーシェはスペインのトーレスコピーですが、後期に自国のフランスのラコートを意識していたとすれば、突然のモデルチェンジも民族意識として何となく納得できます。
トーレスとアルカス
こうして北ヨーロッパではいわゆる19世紀ギターと言われる、ラコートタイプのギターが主流になります。
主に上流階級で人気のあったギターですがいつの間にかブームは去ります。
スペインでは、1800年前後のギターの改革がトーレスタイプの形に落ち着きます。
元々フラメンコや歌の伴奏などで庶民に人気があったギターですが、タレガやセゴビア達により1900年前半に次のギターブームが始まり、トーレスタイプのギターが広まり、今のクラシックギターの幕開けとなります。
トーレスのギターは、当時の19世紀ギターと比べ、弦長を長く、ボディーサイズは大きく(体積増)、表板は薄く、扇形力木やトンネルなどの力木の変更、低いウルフトーン、トルナボスなど今までとは違う発想で作られています。
これらの変化はトーレス一人の発想ばかりではなく、トーレスが手にしたギターから色々なヒントを得て、一つの形として作り出されたものです。トーレスは演奏も上手で、自分の耳で自分にとっていい音を聞き比べ、それをギター作りに生かしたのだと思います。
トーレスはギターによって板厚が幾つもあり、毎回のように変えていたような気がします。
板の硬さで板厚を変えるのは分かりますが、あまり統一感がありません。
修理で薄くなったのも多いですが、当時の道具や計器を想像すると毎回同じ寸法かどうか確認することさえ難しいですし、試行錯誤の表れかもしれません。
材料の荒削りは力仕事で普通は弟子たちにやらせることが多いですが、トーレスには下働きの弟子がいなかったようです。
時にはタンスの板を薄くして使っていたようですが、重労働です。19世紀の後半、産業革命による道具の機械化がどの程度進んだのか分かりませんが、当時のスペインのギター製作家達にはあまり恩恵はなかったような気がします。
しかし材木商の製材機械などには使われ始めていたかもしれません。
ボディーサイズも毎回微妙に違い、しっかりした組み立て用の型を使ってない時期もあったのではと思います。
また表、横、裏の組み立ての順番など今のスペイン的な工法と違う部分もあったようです。
トーレスの経歴は、ロマニリョスの著書に詳しく出ています。ここに簡単な略歴を作りました。
1817年 6月13日 アルメリアに生まれる。
1835年 18歳 大工 フアナ・マリア・ロペス(13歳)と結婚
1845年 28歳 セビーリャへ
1850年 33歳 この頃フリアン・アルカス(18歳)と出会う?
1852年 35歳 この頃から専門の製作家?
1856年 39歳 ラ・レオナ
1858年 41歳 セビーリャ展覧会に出品 ブロンズメダル
1859年 42歳 ミゲル・リョベート(1878~1938)所有
1864年 47歳 タレガ(1852~1909)所有
1869年 52歳 タレガ(17歳)と会う
アルメリアに戻り瀬戸物店 旅館
1875年 58歳 製作再開
1892年 75歳 復帰後155本?製作し、死去
1858年に受賞したブロンズメダルはギター部門で3位だったわけではないようです。
当時ヨーロッパでは各国の珍しい物や、産業革命で生まれた最先端の発明品などを集めた博覧会や展覧会が人気でした。
もし金、銀の賞があるとすれば、最新の時計や印刷機やミシンだったかもしれません。
トーレスは33歳頃にフリアン・アルカス(1832~1882)と出会いますが、その親交は深く、アルメリアに戻ってからも続きます。
アルカスの父親はアグアドのもとで学んだギター愛好家で息子を小さい頃から教えていたようです。
才能のあったアルカスは10代からコンサートを開いています。1863年のコンサートを聞いた少年タレガは感動しアルカスに弟子入りします。
アルカスは当時流行りのフラメンコやオペラの影響を受けながらも、ソルやアグアド達が築いたギター文化を次の世代に伝える大きな役割を果しました。
アルカスの曲をマリア・エステルが弾いたCDがありますが、タレガに繋がる過渡期の音楽は興味深く、ある意味とても新鮮です。
アルカスはトーレスが専門の製作家になるよう助言もしたようです。
二人は新しいアイデアや、その効果などを話し合ったりし、トーレスの製作に大きな影響を与えたと思います。
製作家にとって演奏家の助言は大切で、いい演奏家とめぐり合えるのは運命的であるし、アルカスの助言がなければその後のスペインギターの発展は変わったかもしれません。
トーレスとタレガの転機に関わったアルカスは今のギター文化のスイッチを入れた重要な人物です。
またアルカスやタレガがトーレスのギターで演奏することで、新しいギターの音色が認知され、広まっていきます。
トーレスの後継者とセゴヴィアの出現
1800年後半マドリ-ドでホセ・ラミレス一世がフランシスコ・ゴンサレスの工房から独立して開業します。
フランシスコ・ゴンサレスもトーレスと同じように当時のスペインギターの新しい試みを取り入れ、ギターの大型化や7本バーを試みています。トーレスの存在は知っていて影響も受けていたと思えます。
師匠の教えに忠実だったホセ・ラミレス一世の工房には、ラファエル・カサナ、エンリケ・ガルシア、フリアン・ゴメス、アントニオ・ビウデス、それと弟のマヌエル・ラミレスが弟子として働いていました。
弟は1891年独立して新しい工房を開きます。兄よりは斬新的でよりトーレスを研究し、コピーを試みたり、現在使われているフラメンコギターの基礎となるものも作りました。
当時はフラメンコギターの注文の方が多かったようです。
弟子にはモデスト・ボレゲーロ、ドミンゴ・エステソ、サントス・エルナンデスなどがいます。
ラミレスの弟子達はマドリード派としてスペインギターに大きな影響を与えます。
トーレスは個人製作家でしたがラミレスは分業や機械化を取り入れ、職人達に技術を教え、その生活を支える優秀なマエストロでした。
ホセ・ラミレスの家系は二世、三世、四世と続き、今は三世の娘のアマリアが代表です。マヌエル・ラミレスには子供がなく1代で終わりました。
1912年マヌエル・ラミレスの工房にマドリードのコンサートためにギターを貸して欲しいと、まだ無名の19歳の青年セゴビアが訪ねます。
演奏に感激したマヌエルは一台のギターを進呈し、セゴビアはその後25年間世界各地のコンサートで使用します。
1924年(1923年?)のドイツ公演の時、セゴビアとハウザー一世が出会い、スペイン的なギターの製作のアドバイスをしています。その後もセゴビアはパリやソビエト、ロンドン、アメリカなど世界各地を回り、1929年には日本にも来ました。1936年、スペイン内戦が始まりセゴビアは南米に移住します。
1937年にはハウザー一世のギターに持ち替えますが、セゴビアが納得するギターを作るのに、ハウザー一世は13年かかったわけです。
フランコ将軍を支援するドイツ空軍が内戦中のスペインのゲルニカの町を爆撃したのが1937年でした。
他国の製作家が作ったギターを使おうと決めたセゴビアにも迷いがあったと思いますが、ハウザー一世がとても魅力的だったのだと思います。また南米に拠点を移したセゴビアとハウザー一世との交流は続いたわけですから、二人には民族や政治を超えた深い交流や信頼の関係があったと想像できます。
製作家にとっては、うらやましい関係ですね。
アンドレス・セゴヴィアの活躍
ヨーロッパは1940年~50年頃までは戦争による暗い時代で、ギターを作るのも難しく、その頃の年代のラベルのギターは極端に少ないです。
1944年ニューヨークに拠点を移したセゴビアは、ロドリーゴ、ポンセ、テデスコ、ヴィラ・ロボスなどの新曲や、コンサート、レコードの録音など精力的に活動します。
セゴビアの演奏を聞いて、ギターのためにと作曲する音楽家が現れ、またレコードにより音楽がより簡単に、広い世界に伝わり始めた時代でもあります。
セゴビアは1952年、16年ぶりにスペインに行き、第一回国際音楽舞踊祭に参加します。
この年ラミレス三世(32歳)と会い会食しています。その後幾度もスペインを訪れますが、マドリードに定住したのは1962年です。セゴビアは43歳でスペインを出て、69歳になってスペインに帰ってきたわけです。
祖国を離れたセゴビアの26年間はギターを世界の人に知らしめ、多くのギターファンを作りました。
その功績は計り知れない程ですが、もうひとつギターにとって重大な転換にも関わっています。
それは1946年にナイロン弦を初めて使い、それまでのガット弦に換わる新しい可能性を示したことです。
ギターの音色を変える大問題ですが、セゴビアの音色を受け入れることで、ナイロン弦は瞬く間に世界に広まり、リュートや19世紀ギターでもナイロン弦が使用されるようになりました。
1960年、セゴビアはラミレス三世のギターを使い始めます。
もう一度セゴビアにスペインギターを弾かせたいというラミレス三世の願望は8年かかって叶います。
セゴビアが演奏した国や回数は膨大です。セゴビアの演奏を聞いてギターを弾き始めた人も大勢いました。
日本でも1960年頃からギター人口が急増しました。
それに伴い、ギター製作も盛んになり、世界各地で製作家が生まれます。セゴビアの使用していたハウザー一世やラミレス三世のコピーも多く見られます。
その後も、優れた演奏家が増え、テレビなどのマスメディアの普及にともない、ギター人口を増やし、ギターは一部の民族楽器ではなくなりました。
ギターの製作本数も増え、量産するメーカーも生まれます。1987年セゴビアは94歳で亡くなりますが、その直前まで年間50回ほどのコンサートをおこなっています。超人ですね。
セゴビアの人間性や演奏を批判する人もいますが、批判的なことを言える今のギター文化を築くのには、セゴビアの存在は不可欠です。
日本のギターの歴史
ギターはヨーロッパの文化で育ち、変化してきましたが、後発の日本はその模倣から始まりました。
大正初め頃から外交官が持ち帰ったギターなどで、当事のギターの研究も少しずつ始まっていましたが、戦後、ギターが大ブームとなります。
初めは演歌や流しの伴奏で、その後フォークギターやエレキギターも流行り、若者がいる家庭には一台はギターと名のつくものがあったのではと思えるほどでした。不良の始まりだと親に言われエレキギターを諦め、アコースティクギターを始めた人も多くいました。練習し始めて、イエペスやセゴビアなどのクラシックギターの世界を知り魅了された人も沢山いました。
人口の多い団塊の世代の青春時代の頃の話です。映画スターはギターを弾き、テレビではNHKでギター教室が始まり、雑誌には通信教育(ソノシートで)の広告もありました。楽器屋の量販ギターにはスチール弦が張ってあるクラシックギターや白色のもありました。
当時のクラシックギター愛好家達は、人口増を歓迎しつつも複雑な思いもあったようです。
当然製作家も増え製作台数も増えます。需要に供給が追いつかず、とりあえずギターの形で弦が張ってあるだけでも飛ぶように売れた時代もあったようです。いいものをと志した製作家の中には高価な舶来ギターを分解し、研究した人もいたようです。
当時はスペインの伝統的な工法を知りたいと思っても、閉鎖的なヨーロッパで日本人が親しく付き合うには、情熱だけでは無理がありました。長い船旅や、フランコの独裁などの不安定な政治事情、仲間意識の強い職人たちに認めてもらえる語学力、など幾つもの障害がありました。
西洋の音楽が日本に入ってくるにはその音源が必要です。レコード、テープ、映像など聞くことが出来ますが、それを輸入した人々がいました。
演奏家を日本に連れてくる為に、招致の交渉をした人々がいました。外国の楽器や楽譜を輸入した人々もいました。そして外国で音楽の勉強をしたいと留学する演奏家も増えてきます。
そんな先人達が築いた人脈を頼りに、ギター製作を学びにスペインに渡った製作家が何人かいました。
彼らは目に見えない部分を学んで持ち帰りました。
その中に禰寝さんがいます。出会えたのはアントニオ マリンですが、マリンの人柄や、マリンにつながる人脈など幾つもの偶然が重なった結果です。
スペインの製作家の仕事場で、現場そのものを体験出来るだけでも貴重な経験ですが、禰寝さんの語学力はもっと深い理解や関係を作れました。スペインの文化、風土、気質、そして何よりスペインの伝統的なギター製作の方法を体で感じ、理解出来たのが禰寝さんのような気がします。
帰国した禰寝さんはスペインで学んだ工法のまま、同じペースで製作します。
当時の日本流の製作方法と違い効率が悪く、持ち帰ったままでは日本のギター文化になじみません。例えば、セラック塗装のギターはメンテナンスの問題もあり、お店に置かれるのは一部の輸入ギターだけでした。
今ではすべてセラック塗装の国産ギターを見かけることも多くなりましたが、当時は、白くなったとか、傷がすぐ付くとか、セラック塗装のよさを理解出来る人や塗れる職人も少なかったのです。修理や転売時に固い塗装に変えられてしまうギターが沢山ありました。しかし情報が増えるにつれて、粗製乱造の手探りだった日本のギターは少しずつレベルが上がります。
留学から帰ってきた演奏家が活躍し、演奏会やコンクールも増え、ギター文化の質も高くなります。模倣から始まった日本のギター文化ですが、今では海外からも高く評価される演奏家や製作家が何人もいます。
ギター構造の新しい発想
1900年後半の世界的なギターブームは、ギター製作の伝統のない国でも起こり、それぞれの国で初代となる製作家も生まれます。
彼らはお手本となるギターをコピーすることから始めます。民族意識の強いヨーロッパの製作家の元で修行するのは難しいですから、それぞれの国でそれぞれの方法でギターを作ります。
それはある意味でそれらの国でよしとする音色です。演奏者のレベルや、聞き手の求める音色や、売りやすいギターの値段など要素は色々ですが、それがその国の文化になっていくわけです。
しかし伝統のない新しい国では、新しい発想でギターを作れる環境でもあり、今までに無いギターを作る製作家も現れます。
ギターは弾き込みで音が変化します。その変化は少しずつで、日々弾いている時間や、構造やタッチで変わる時期は色々ですが、ある時(弦を張り替えたときなど)音が変わったと実感するときがあるようです。
松と比べ杉のギターは弾き込みの変化が少なく初めからよく鳴りますが、弾き込むことで音がつぶれ、へたるのも早いと言われています。
新作の松は弾き込みの変化を予想して手に入れなければならず楽器選びが難しくなります。
杉は最初からよく鳴りますが、他にも新しいタイプで何処かにアンプでもあるのかと思える様なよく鳴るギターがあります。
それはオーストラリアの製作家、グレック・スモールマンのラティスとかワッフルと言われるタイプです。
これは表板を極薄(0,5ミリ位?)にして、格子状の力木で強度をつけてあります。
裏板は厚くヴァイオリンのようなアーチがあります。重量は重く、薄い膜を重たい箱で鳴らすスピーカーの発想だと思えます。
スモールマンは色々な試みをします。同じ裏、横で表板だけ取替え、板厚と力木の関係を調べ、カーボンや粘土(ウルフトーンの調整)なども使用します。
スモールマンはヨーロッパを中心とする伝統的な工法の流れと違う新しい発想でギターを作りました。
それをジョン・ウイリアムが使うことで世界に知れ渡ります。
今までと違う新しい音は、賛否両論で迎えられます。軽いタッチでも気持ちよく鳴るのは麻薬的に気持ちがいいのですが、音色の変化は少し乏しいです。
昔のジョンの音の方がいいとか、愛国心が強いからとか、セゴビアに対する反発で違う音色が欲しかったとか、色々な意見が聞かれました。
古いクラシックギターのファンからはスカイを結成したころから異端視される向きもありました。
ジョンがステージでPAを使用することにも反論する人がいます。ジョンぐらい上手ければ楽器の違いはあまり関係ない気もしますが、ジョンが選んだことで今のスモールマンがあるわけです。
ヨーロッパの秘密主義的な製作家と違い、スモールマンは技術を公開します。
もともとギター製作の文化が薄かったオーストラリアですが、今ではラティスタイプの製作家が沢山います。
勿論、ヨーロッパの伝統的なギターを研究しているオーストラリアの製作家もいます。
スモールマンの次に現れたのがドイツのマティアス・ダマンです。
初期の頃はトーレスのコピーもしていましたが、新しい表板の試みをしました。
ダブルトップと言われる表板は3層になっています。中心の層はカーボンファイバーシート(デュポン社のNOMEX)で上下は松や杉を貼り合わせています。
従来の板と同じ厚みでも軽くて丈夫になるようで、力木の配置や構造は同じでも鳴りが良くなります。
シートの形や面積は色々で、接着剤の種類や方法も色々なようです。ダブルトップの組み合わせだけでも、松松、松杉、杉松、杉杉の4種類あります。多分、色々な組み合わせを色々な接着で試行錯誤している製作家は沢山いると思います。
普通にギターを作っていても、表板の持つ個性は多様で力木との組み合わせで無数の音色になる気がします。
そこに新しい無数の個性を持つ表板が加わるのですから益々複雑になります。
全体の印象としてダブルトップはよく鳴ると感じるだろうな、と思います。
よく鳴ることだけで良いギターとは言えませんが、よく鳴る音色の違いを言葉にするのも難しいです。
ギターの音色の変化は過去の音色を否定することではないと思います。
古いタイプの音色でも、とても魅力的です。ラコート、トーレス、ハウザーと大雑把な音色の違いに分けても優劣を付けるのは難しいです。
この音色の変化を、大きな音量を求めた結果だと説明している人もいます。
でも、コンサートでより多くの聴衆に聞かせたいという、経済的な理由ではない気がします。
かりに大きい音がいい音だとしても、ギターに求める音量には限界がありますし、PAに頼ると割り切れれば、ギターに音量は求めなくてよくなります。
19世紀、ホールで音楽を聴く文化が庶民に広まり、オペラやオーケストラのコンサートが人気を集めるにつれて、19世紀ギターの人気は下がります。
ギターの音量は小さく、持続音も短いのでオーケストラの楽器の仲間入りは出来ませんでした。
オーケストラの楽器は基本的に旋律楽器で独奏は苦手ですが、ピアノは複雑な和音も出せ、独奏楽器としての強みがあります。
でもピアノは音量の変化はあるものの、音色の変化は乏しいです。
そんなピアノ奏者もうらやむギターの音色の変化は大きく、ビブラートもかかります。
独奏楽器としてのギターは魅力的で、ソルやアグアドがオーケストラ楽器の仲間入りを望んでいたとも思えません。
19世紀ギターの衰退とオーケストラ文化の人気は関係していても、ギターの音量の大きさはあまり関係ない気がします。
現代ギターの原型トーレスと系譜
昔、ドキッとするようないいトーレスを弾いたことがあります。
今のギターの原型であるトーレスの音にはある程度イメージがあります。
なんで「ある程度」なのかは、時代が作る部分を省いた、出来上がりの時の音は想像でしかないし、その後の修理の影響で大きく音色が変化しているかもしれないからです。
ナイロン弦で今の自分のタッチで弾いて、トーレスの音を聞き比べても、すべてがいい音だとは思えません。
それはもともと出来の悪い楽器か、管理、修理に原因があります。トーレスも新しいアイデアを試したり、止めたりと色々なタイプのものを作っています。
でも幾つかのトーレスを聞くと何となくひとつのイメージが出来ます。沢山聞けばより鮮明になりますが、状態のいいトーレスは稀ですし、トーレスの音を聞く機会も少ないです。
少し時代がずれますが、サントスの音を聞く機会の方が多くあります。
1916年52歳の若さでマヌエル・ラミレスが亡くなったあとサントスは自分の工房を作ります。サントスの作ったギターはトーレスと比べ華奢で、低音は重く、乾いた音色で、同時代のエステソ、ガルシアなどもウルフトーンの位置の低い、同じような傾向の音色です。
勿論サントスの音色にも色々ありますが、トーレスより少しはっきりしたイメージがあります。
曖昧なイメージですが比べると、トーレスの音色は甘く、丸い感じで、サントスは乾いた、枯れた感じです。
もっと曖昧で個人的なイメージで言うと、トーレスはヨーロッパ的で、サントスはスパニッシュな音色に感じます。
現代ギターの父とも言われるトーレスですが、同じように現代ギターの父と言われるタレガなどの演奏家に新しく魅力的な音色として認められ、トーレスをコピーする製作家が増えます。
これは主にスペインの流行の音色のようでした。そんな流れの中でマヌエル・ラミレスもトーレスの影響を受け、手本としながら、オリジナルな音色を探り、当時のフラメンコギターも大型にしたりして工夫を加えます。
そのラミレス工房の職人の一人がサントスです。工房の中でもサントスの技量は高かったと思いますが、セゴビアが使ったラミレスラベルの製作者がサントスだったことでも、サントスの名前がより広まったのだと思います。
セゴビアがマヌエル・ラミレスのギターで演奏していた時代には、まだそのまま現役で使えるトーレスがあるはずです。
当時、有名なトーレスを弾く機会はあったはずですが、コンサートの演奏では使用してないようです。
金銭的な事情があったのか、マヌエル・ラミレスを手に入れる経緯を大事にしたのかはわかりません。
セゴビアが使った1912年のラミレスは11弦ギターを改造した痕跡のあるヘッドで、構造はほぼトーレスコピーです。
音色も同じ傾向だから、セゴビアはあえてトーレスに持ち替える必要を感じなかったのか、タレガやタレガ門下の多くが愛用しているから、あえて使いたくなかったアンチタレガだったのかもしれません。
セゴビアは1893年にリナレスで生まれますが、2歳の頃伯父夫婦に預けられ、親元から離れて育ちます。
セゴビアのフルネームはアンドレス・セゴビア・トーレスです。母方の姓と同じトーレスを使わなかったことと、幼少期の環境とは関係なく、単純に気に入るのがなかっただけかもしれません。
ギターのサウンドホールの上下には、表板の木目と直角になる方向に太い力木を貼ります。
平行なものが多いですがそうでないのもあり、アメリカに渡ったマーチンはサウンドホールの下に2本の力木でXの形にしました。
19世紀ギターは、駒の辺りにも同じような太さの力木を1~2本貼ったものや、何もないものもあります。
駒の辺りに貼る力木は斜めにしたものもありますが、表板の高音側と低音側での振動をイメージしてより効率的に振動させようとして斜めにしたのだと思います。
面白いのはパノルモとラコートで斜めの向きが逆になっているのがあります。二人のイメージが逆なのか、ひょっとして左利き用かもしれませんね。
トーレスは駒の辺りに、割り箸位の細い力木を7本(5本のもあります)、扇形にして貼りました。
これはトーレス以前にも似たようなものがあります。たぶんサンギーノやパヘスのイメージの延長です。
幾つものタイプを作り分けていたパノルモも同じような7本バータイプも作っています。
駒とサウンドホールの間の表板は弦の張力で凹んできます。
19世紀ギターは厚めの表板や、横に渡した力木でささえますが、7本バータイプは薄めの表板で、力木を細くし数を増やすことでより弾力を付けてささえます。
扇型のタイプは力木の本数や貼る位置で幾つものパターンがあり、製作者の個性が出ます。
力木は5、7,9本の左右対称なのが多いですが、6、8本の非対称のもあります。
普通、扇型の要はヘッド方向にありますが、反対のエンド方向にしたものもあります。
力木を一本一本見ていくと、幅や高さや断面の形など色々違います。表板にどのような硬度を持たせたいのか良く分かる力木の配置もあれば、意図が分からないものもあります。
板厚や力木の配置や太さは、音色を決定する重要な部分ですが、それぞれの製作家によって、無数のイメージがあります。
トーレスとサントスの音色の違い
サントスはトーレスやマヌエル・ラミレスを手本としながらも、より表板を華奢にしました。
トーレスとサントスの音色の違いは、ボディーサイズや構造の違いとして目で確認できます。
ですから、力木の位置やサイズなどコピーすることは出来ますが、板厚など細かなところまでは不可能です。
見た目はそっくりに作ることは出来ても音が同じになるとは限りません。
そこがギターを作る立場としてとても重要な問題になります。
コピー元にばらつきがあり、コピーして作ったギターはそのばらつきの範囲と思える人もいます。
同じギターでも、違うイメージを持っている人から見ると全然似てないと思えることもあります。
また弾きこむことで音色は変わりますから、10年弾いて似てくるとしたら、10年待たなければならなくなります。
その頃にはコピー元も10年分変化しているので厄介な問題ですね。
トーレスとサントスの違いは、作り方、膠、塗装、材料の選別など寸法としてコピーできない部分にもあります。
塗装がオリジナルというのは殆どなく、比べるのは難しいですが、元はどちらもセラックで大差がない気がします。
膠もセラックと同様ですが、細かな種類の違いや濃度までは本人に聞かなければ分かりません。
大きな違いと思える作り方も、聞いてみなければわかりませんし、材料も数枚の表板からどれが好みか二人に聞いてみたいですね。
これらの目で判断出来ない違いはトーレスとサントスの音色の違いに関係しています。
寸法の違いよりもっと多く音色に影響しているかもしれません。肝心な部分は本人しか知らないのは残念ですが、製作者はその違いを想像し、求める音色作りを楽しんでいるわけです。
違いを比べるには、ウルフトーンの位置やタッピング音も手がかりにします。コピーを製作するときは、ウルフトーンの位置も同じにしたいわけですが、なかなか難しいです。
それはウルフトーンに影響する要素が多いからです。仮に、同じ寸法で、同じ塗装で、目に見える部分を同じに作れたとしても、ウルフトーンの位置や音色が同じになるとは限りません。
それは、材料の木の違いなどにも原因があるからです。材質の違いは、乾燥レベルや比重、木取り、木目など色々で厳密には同じものはありえません。
材質の違いはタッピングの音を聴いて大まかなイメージで聞き分けます。
材料のタッピングの音と出来上がったギターの音の間には無数の因果関係がありますが、結果としての音色はひとつです。
同じ構造、工法で何台も作ると表板の材質の影響が何となく繋がります。
求める音色に合った板で、求める音色が出来れば製作者としては大満足です。
ウルフトーンの位置が同じでも、音色はひとつではありませんが、音作りにおいてウルフトーンの位置やタッピング音は重要な手がかりの一つです。
ヘルマンハウザー
先日、ハウザー一世の1938年を弾いてみました。一世のものは少なく、久しぶりでした。
イメージしていた音に近く、「やっぱりいいな~」と再確認しました。ハウザー一世は37年の楽器をセゴビアが使用したことで有名になりましたが、その前はトーレスやサントスのコピーを作り、スペイン風の音色を試していました。その前はウインナーモデルと言われる、19世紀ギターのシュタウファー(ドイツ)風の楽器も作っていました。
ヘルマン・ハウザー一世(1882~1952)の父親ヨゼフ・ハウザー(1854~1939)はチター奏者で、チター製作者でもありました。チターの為の作曲をし、その曲の出版社も設立しています。
ハウザー一世はそんな父親の工房を引き継ぎながらギターやリュートの製作を始めます。
また演奏も得意で、ミュンヘン・ギター三重奏団(四重奏団?)の一員でした。
ハウザー一世の作ったギターの中のウインナーモデルと言われるものは、胴の厚みは薄く、小ぶりなグラマラスな外観で、多分スチール弦を使用していたと思われます。
ウインナーモデルは、19世紀的な力木で井桁に組まれ、表板は厚く、叩くとコンコン硬い音がします。
ハウザー一世が仮にサントスのフルコピ-をしたとすれば、表板が変形しそうで不安に感じただろうと思います。
木を削る時、目標の寸法より少し手前になりがちですが、それは削り過ぎると元には戻らないけど、手前なら後から削れるという心理があるからです。華奢に作るのは割りと勇気がいるものです。
ハウザー一世は、工作精度の高さをセゴビアに見込まれ、スペイン風な楽器の注文を受けたのだと思われます。
ハウザー一世もセゴビアの演奏に感動し、セゴビアの使用した楽器のコピーや、当時のスペインの楽器の研究をしています。
その頃のギターを何台か見ましたが、あまり音色が似ていません。
サントスコピーでは、力木の配置は同じようですがウルフトーンの位置が高く、スパニッシュな音色ではありませんでした。
また、トーレスをコピーしたようでもオリジナルな部分があり雰囲気がちがいます。
数多く見たわけではないので解かりませんが、もともとフルコピーするつもりがなかったような気もします。
さもなければコピーには限界があり、スペイン的な音色が出せなくて諦めたのかも知れません。
仮にそっくりなギターが出来ても、セゴビアがドイツの楽器に持ち替えるとも思えませんから、ひょっとしたらセゴビアから求める音色の改良点を言われていたのかもしれません。
だとしたら、スペインの製作家にも同じ問題点をアドバイスしていたはずです。
たぶんスペインの製作家もセゴビアに選ばれたマヌエルの秘密を探し求めながらも、それを超えるために試行錯誤をしていたのだと思います。
37年のハウザー一世にはトーレスやサントスにない新しい工夫が見られます。
それは駒より少し長い大きさの薄い板を表板の駒の位置に合わせて貼ったことです。
駒下を貼った部分だけ表板が厚くなったわけです。
19世紀ギターの中には今のフォークギターのようなピンで弦を留めるものがあり、表板に開けた穴の補強に小さな薄い板を貼ってあるものもあります。
たぶんハウザー一世はそれをヒントにピン留めの補強と違う目的でイメージしたのだと思います。
ウインナーモデルを作っていた経験のあるハウザー一世だから出来た発想だと思えます。
1919年のソロモデル(?)には駒下があります。このギターは修理の手が入っていてはっきりしませんが、この頃にはすでにイメージがあったのかもしれません。
目でわかる大きな違いは、ハウザー一世の発案だと思いますが本当かどうかはわかりません。
でも元々丈夫な楽器を作っていたハウザー一世が華奢に作る事にためらいを感じ、ウインナーモデルを作っていた時のイメージを融合したことにより、セゴビアも納得する新しい音色が出来たのだと思います。
スペイン人の演奏家がドイツ人の作った楽器を使っているのは愛国心の強いヨーロッパですから、不満に思っているスペインの製作家も多かったはずです。
セゴビアがあえて使用するほど魅力を感じたハウザー一世の楽器は多くの製作家に影響を与えます。
それは目に見えて強烈な変化でした。1936年のスペイン内戦から20年程はギター製作に関しても暗い時代で、次の世代に上手く伝えられずに終わってしまった製作家もいます。
しかし政局が安定し始めたころ製作されたギタ-の多くには駒下が付いています。
1912年マヌエル ラミレスにギターを譲られてから75年間、セゴビアに弾かれたギターは製作家や演奏家に注目され続けます。
1937年セゴビアがハウザー一世に持ち替える事で、ハウザー一世は注目の的になります。
マヌエルとの音色の違いは聞けば解かるし、セゴビアのお墨付きもある訳で、今度はハウザー一世のコピーが増えます。
ホセ・ラミレス
1960年セゴビアがラミレス三世に持ち替える頃にはハウザー一世の新しい試みは、ギターの力木の定番として多くの製作家に広まります。セゴビアが使用したラミレス三世は20回以上、新しいものと換えられました。
それはラミレス三世がいくつもの新しい試みをし、そのつどセゴビアが気に入ったものと交換していたからです。
この頃はフレタも使っていてラミレスはライバルとして意識していたようでした。
新しい試みには、表板を杉にしたり(1965年頃)、側板を合板にしたり、カマラという側板の間にキャットウオークのようなものを付けたのもあります。
1985年頃完成したカマラはセゴビア(92歳)も絶賛し、ラミレス三世(63歳)も納得する楽器でしたが、今は作られていないようです。
ラミレス三世とハウザー一世を比べると、サウンドホールの下の力木から高音側に向かって斜め下に、もう一本太い力木が増えています。
同じような発想は、フレタやアグアドにも見られます。時期が近く誰が最初かよく分かりませんが、たぶんラミレス三世ではないかと思います。
サントスの作ったものにサウンドホールの下の力木を単純に斜めにしたのがありますが、それをヒントにしたのかもしれません。
そのサントスも19世紀ギターの斜めに貼った力木を参考にしたのかもしれません。
他にも分かりやすい違いは、弦長が長くなり、ボディーサイズが大きくなり、塗装が硬くなったこと等です。
ラミレス三世の1960年頃のギターのウルフトーンの位置はソ♯前後が多いですが、1937年あたりのハウザー一世はソ前後です。
同じような構造でボディーサイズを大きくするとウルフトーンの位置は下がりますが、ボディーサイズが大きくなったのにウルフトーンの位置が上がるのは、表板が丈夫になったことが関係しています。
ちなみにサントスはファ前後が多いです。ラミレス三世が新しい試みをするたびにウルフトーンの位置は少し上る傾向があります。
面白いことにハウザー一世も二世、三世と時代が進むに連れて上がっていきます。
ウルフトーンの位置と音色の関係を説明するのは難しいし、ギターの良し悪しとはあまり関係がありません。
でも大まかなイメージとしてウルフトーンの位置が上がると、サスティーンは長くなり、弾いたときのパワー感が増します。
ウルフトーンは表板の材質、厚み、力木の配置、寸法、他にも横板、裏板、塗装などで変化し、影響する度合いもそれぞれ違います。
たぶん時代もウルフトーンの高いギターを求めていたのかもしれません。
ギターの音色と製作家が目指すもの
ヨーロッパの製作家には先人達が築き上げてきた伝統があります。
時代の変化や演奏家の影響で少しずつ変化してきましたが、昔の音色の方が好きな製作家もいます。
今でも、トーレスやサントス、ハウザー一世タイプの楽器を作る製作家は大勢います。
少しでも良くしようとして改良をされ続けてきた音色には、ギター本来の魅力の一部が失われてしまったようにも感じます。
客席で聞くと、十分よく聞こえて来る19世紀ギターや古いギターがあります。
そのギターがどの位大きなホールでも聞こえるのか確認しづらいですが、弾き手のタッチの違いのほうが大きく影響すると思います。
舞台の上で弾き手がパワーを感じる音と、客席で感じる音圧は違います。
大きく聞こえてもモコモコした音では感心しません。ホールで聞いていて、いいギターやいいタッチの音は、目を瞑って聞くと実際の距離よりも近くで弾いていると感じさせます。
遠達性のいいギターは不思議と小さい音でも同じように距離感は近く感じさせます。
個人的には、ギターの音量を上げて、無理して大ホールで弾くより、ギターに合ったそれなりの大きさのホールを選んで弾いたほうが、ギターの魅力を伝えやすいと思います。
また、録音された音色を生のギターに求める傾向があります。
録音された音はホールの残響が入っていたり、加工された音かもしれません。
自分で弾いて聞いた音と、スピーカーから聞こえる音は同じにはなりません。
だから単純に時代が求める音だからといっても、すべていいとは思えません。
絵画の基本がデッサンであるように、ギター作りはコピーから始まります。
師匠の真似をすることで道具の使い方、調整、砥ぎなど基本的な技術も学べます。
教わるのではなく、盗めと言われますが、理屈を自分で考えたほうが身につきます。
道具とか工法はそれまで伝えられた伝統があり、伝え続けられたものにはそれなりの意味や価値があります。
近代化により新しい価値が生まれれば、古いものは消えていき、意味も判らなくなります。
バロックギターや、リュートなどの古楽器の文化は個人的な努力や興味が支えている気がします。
ヴァイオリン製作家は過去の名器を研究し、秘密を探り、その再現を求めているように思えます。
ヴァイオリンと違ってギターは新しい音色を受け入れる土壌があります。
その柔軟性は19世紀ギターの衰退にも関係していると思いますが、トーレス以降の今のギターの音色の遍歴にも影響しています。
大衆の生活に密着しているギターはその時々の流行に影響され、選択される音色の幅はどんどん広くなりました。
単音の音色は個人的な好みで、自分のタッチと相談して選べます。個人的な好みの音色を見つけたら、その音色が持っている性能を聞くことが必要です。
譜面の中の、旋律以外の音が聞きとりにくいとか、音色の変化やダイナミックレンジの幅が狭いのは、ギターの性能にも関わってくるからです。
演奏家の心の内に在る音楽を表現する手段としてのギターなら、製作家としては求められる性能は満たしたいです。
演奏家もそのギターの性能を十分に発揮させるために、爪やタッチを工夫しています。
いい演奏家はギターによってタッチを変えます。また、名器は演奏家にタッチを教えるとも言われています。
製作する立場で、まったく新しい音色を見つけられれば面白いかもしれませんが、過去の音色に学んで、新しい試みを加えるのも面白いです。そして、演奏家の表現の手助けとなれるのが一番です。