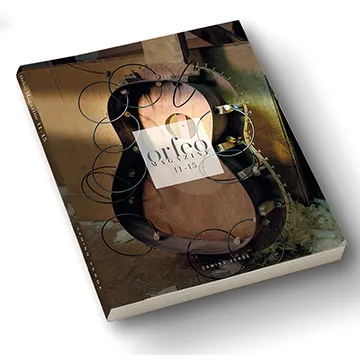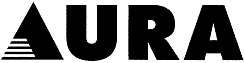「Orfeo」という雑誌をご存知ですか?
フランス、パリのアート系書籍の出版社Camino Verde社が2013年より年2回のペースで発行しているクラシックギターの専門誌です。
と言ってしまうとどこの国にでもある、いわゆる演奏家、作曲家と楽曲、コンサート情報と愛好家どうしのコミュニティが主なコンテンツである普通の音楽雑誌を想像しますが、この「Orfeo」は徹底的にギターという楽器と製作家、そしてそれらの背景となる伝統と文化とをメイントピックとした独特な編集方針とその充実した内容で、ヨーロッパをはじめとする世界中で高い評価を受けている雑誌です。何より素晴らしいのは、トーレスなどの何人かの歴史的な銘工を除き、取り上げられている製作家のすべてが現役であること。そして彼らの製作に対する美学と哲学、ギターの特徴(その作り手にしかわからないような)、製作家としての歩みなどを簡にして要を得たインタビューで紹介するとともに、まさにそれらの楽器が生み出される現場としての工房を、生々しくも美しい写真で伝えていることでしょう。
これらのインタビュー、写真撮影からおそらく全体のアートデイレクションもつとめているAlberto Martinez 氏(御年75歳!)は、ほんの何年か前までBMW、MINI COOPER、CITROENなどの高級車のオフィシャルイメージとなる写真を撮影しておられたプロカメラマンで、その腕前はもちろん、写真というアートだけが為しうる表現に対するこだわりとその審美的センスは素晴らしく、彼によって撮られた工房の写真はそのさまざまな道具から作業台に刻み込まれた傷に至るまで、職人の手が生み出した時間のトレースとしての光彩を放っています。もちろん楽器本体の写真の美しさ、書物全体としてのレイアウトや構成もやはり特筆すべきもので、アートブックとしても永久保存版にしたくなるほどのクオリティを創刊から現在まで維持し続けています。
それぞれ合冊版として1冊にまとめたものが出版されており、現在アウラ店頭とオンラインショップにて入手可能です。
このOrfeo Magazine が日本の製作家を特集する号を企画しているとAlberto 氏からAURAにオファーを頂いたのが一昨年の2018年。日本のギター製作の現状とこれまでの歴史を私たちと相互に確認を取り合いながらお話を進めさせていただき、そして彼はアルベルト・ネジメ・オーノ(禰寝考次郎)、尾野薫、田邉雅啓の3人を取り上げることを決定します。資金繰りやスケジュールの調整などの困難があり企画自体が一時危ぶまれたものの、なによりもAlberto 氏の情熱がすさまじく、遂に今年に入り来日が決定、次号での日本特集に向け、数日に及ぶ来日取材が行われました。
取材を行ってゆくうちに3人の他にもその次を担う世代の製作家達として、禰寝碧海、栗山大輔、清水優一もまた誌面で紹介してゆくということになり、AURAは彼らすべての工房での取材に同行しました。2020年初夏に発刊される予定の次号 Orfeo Magazine 日本特集号に先立ち、これから数回にわたりその取材の様子をお伝えしてゆきます。
写真は尾野薫工房での撮影風景、AURAショップでのAlberto氏と田邊雅啓、3枚目はPCでデータを見せながら製作家と(右から尾野薫、中野潤、Alberto氏、田邊雅啓)



「日本の製作家」特集 取材レポート 尾野薫 編
フランス、パリのCamino Verde社から出版されているクラシックギター専門誌<Orfeo>
いま世界中のクラシックギターファンから注目されるこの美しい本が、次号にて日本の製作家を特集する事が決定!!
この本の編集長であり、カメラマンとインタヴュアーも務めるAlberto Martinez 氏の取材に同行し、その現場をレポートするエッセイ。第一弾となる今回は尾野薫工房 をご紹介。
「Kaoru Ono とはどのような製作家なのだろう?」
Alberto 氏が宿泊する都内のホテルに迎えにゆき、車に機材を積むまでの間にロビーでこれから訪れる尾野氏のことについて会話が弾んだ、既にAlberto氏は真剣そのものの表情。
「ギターにとってのあるべき音響、音色について、とても明確な哲学をお持ちの方で、実際にその完成度は世界レベルの素晴らしいものだと思います。きっと面白い話が聞けますよ」
車で世田谷区にある尾野氏の工房に向かう、その車中も静かな期待が充満しているように感じられる。閑静な高級住宅街ですが、氏の工房は車一台やっと通れる道を入って行ったところにあります。建物の外観は作業場然としたところはなく瀟洒な雰囲気、しかし玄関を入り通された一階の工房にはさすがに繊細な空気感が漂っています。塵ひとつなくすべてが整理整頓された空間というわけではなく、work in progress の工房の生々しさがありつつも、無造作に置かれたかに見える工具や書物でさえもが製作家の意識の流れを感じさせる。広すぎず、また狭すぎずいい按配の空間の中に、製作に必要な工具や作業台や作りかけのギターたちがあるべき場所に収まって製作家の仕事を待っている様子は、名演奏家が長年愛用している楽器のような、独特の有機性が生まれていて何とも心地よい空間。
Alberto氏は鋭い眼で工房を眺め、まずは完成したギターを試奏。
「とても美しい音だね」
そしてインタヴュー。尾野氏が製作を始めたきっかけや影響を受けた製作家またはギター、自身の楽器がどのようなものか、音について、使用している工具について、モデルごとのレゾナンス設定について等々の質問と答え。隣で聞いていても本当に面白い。音については尾野氏が実際に和音と単音、分散和音、和音進行の中にメロディーがどのように表れどのようにそれぞれの音が響くべきかなどを演奏してデモンストレーション。
この後は写真撮影となり、Alberto 氏自らが撮影するのですが、あの美しい写真たちがどのように生まれてくるのか、興味津々だった筆者はここで見る本当のプロの仕事に心底感心してしまった。必要最小限の機材(ほとんどローファイとさえ言いたくなるような)だけを用い、被写体をどのように配置させるかをすばやく緻密に計算して、あとはシャッターを押すだけ。無駄がなく、被写体に配置には少々演出が加わるものの、自然なたたずまいを損なわず、むしろモノとしての別の表情を見せてくる。
Alberto氏が工房の中でとりわけ強い興味を示したのが工具です。


尾野氏が使用する工具は日本製のもので、それは外国製のものとは、例えば同じ鑿でも決定的に違うそうです。それ自体が工芸品とさえ言えるそれらの工具がその審美的な美しさでAlberto氏を惹きつけたのはもちろん、その「用の美」としての工具の特徴がどのように製作上のメリットがあるかについては、大きな示唆を受けたようです。氏は今回の来日で鍛冶屋のほか博物館などで工具のアーカイブを見る機会も準備しており、日本特集号では一つの独立したトピックとして取り上げる予定とのこと。
工房での取材を終えた後、尾野氏が懇意にしている土田刃物店に尾野氏も同行して向かうことになりました。三軒茶屋駅の目の前を通る世田谷通り沿いにあり、何時も非常な賑わいを見せる商店街の中にあるのですが、よく見ていないと通り過ぎてしまいそうなたたずまい。2人も入ると一杯になる店内は雑然としていてどこからが商品でどこから私物なのかが判らないほど。古本なども無造作に積み上げられていますが、これは売り物なのでしょうか?(ジョルジュ・バタイユの文庫本まである)。
すごいな、と思ってAlberto 氏をみると彼はいかにも深く感激していて、誠実にものを売っている店のあるべき姿だと言わんばかり。
「パリで卓球ラケットの専門店があるんだが(Alberto氏は卓球も結構な腕前のようです)、そこはこことよく似ている。狭い空間にあふれんばかりのラケットが無造作に積み上げらているが、扱っているのは厳しい店主の目にかなう一級品ばかりなんだ」。
店主の土田氏のご好意で、店内で工具を撮影、なんと自ら鋸を1丁購入。

手ごたえを感じた取材の後、三軒茶屋駅ビルの最上階の展望レストランで軽く休憩。ちょうど夕刻で眼下の建物には明りが灯り、東京の夜景を楽しむ。パノラマの全景が楽しめる趣向なので、スカイツリーと東京タワーから丹沢の山々までが一望に。その中で氏が「あれは何だい?」と指差した密集した高層ビル群、「あれは新宿副都心ですよ」と私が答えると、Alberto氏は何か異様なものでも見たような表情になり、「すごいな、あれは」と一言。
(実は後日、取材の合間に彼は新宿を訪れるのですが、信じられないほどの人出とこの街の異様なパワーにほとんど感動さえ覚えたようです。そしてこの新宿のイメージが、我々日本人を代表するものの一つとして、日本特集号で掲載されることになります。その日本的イメージとしての「新宿」とは…)
夜景を見た後、取材を終えて楽しげな氏はいかにもパリジャンらしく(勝手なイメージですが)カプチーノを注文。
氏は今回の滞在中、一服の際にはいつもカプチーノを注文していました。
「さあ、カプチーノタイムだ!」

「日本の製作家」特集 取材レポート 禰寝孝次郎 編
フランス、パリのCamino Verde社から出版されているクラシックギター専門誌<Orfeo>
いま世界中のクラシックギターファンから注目されるこの美しい本が、次号にて日本の製作家を特集する事が決定!!
この本の編集長であり、カメラマンとインタヴュアーも務めるAlberto Martinez 氏の取材に同行し、その現場をレポートするエッセイ。第2弾となる今回は禰寝孝次郎(アルベルト・ネジメ・オーノ)氏の工房 をご紹介。
製作家 アルベルト・ネジメ・オーノ(本名 禰寝孝次郎) 氏は、日本が本格的なスペインギターの伝統を受容していく決定的な契機となった人である。そのことは昨年に弊社ギターショップアウラが発行したオリジナルカタログ ‘ LAS GUITARRAS ’のなかのエッセイ「ギター製作の伝統と現在 ~スペインから日本へ~」の中に詳しく述べられているのでご参照いただけたら幸いです。
今回Alberto Martinez 氏から取材オファーをアウラ宛てに頂いた際に、まず思いついたのが禰寝氏でした。現在は本数を抑えているものの、充実した仕事を続けており、そして後進の指導とその影響の大きさも計り知れないものがあります。そしてなによりも比肩するもののない美しさと威厳を持つ、艶を湛えた重厚な響きのギター。伝統的でなおかつ進取に気性さえ感じさせるそのギターこそ、日本のギター製作の現在における最高の成果として提案できるのではないか、という思いが我々には強くありました。
取材当日は朝から雨。前回同様に都心のAlberto氏のホテルにまで車で迎えに行き、近くの高速入口から高速道路で2時間ほど。Alberto 氏は窓の外を過ぎる雨の風景にも静かに感じ入ったご様子だったのを見て、私は前日に氏からプレゼントされた写真のことを思い出していました。それはどこかの国の、なだらかな傾斜に拡がる森が白くうっすらと霧に覆われている風景の写真で(というよりあまりに繊細な画像の肌理に絵画なのかと一瞬思い)、私はすぐに日本の水墨画のことを思い出しそのことを氏に伝えると、
「そうなんだ、私も水墨画のことは知っている。でもねこれは実はスペインの森の風景で、しかもれっきとした写真なんだよ」
高速道路の車の外に雨靄に白く煙る山々が現れ出すと、
「昨日君に渡した写真と同じだね!」
と後部座席からAlberto氏が嬉しそうに話してきます。まるで今日のことを予想していたようでした。
禰寝氏の工房はごく普通の閑静な住宅街にあり、住居兼工房となっています。その昭和なたたずまいに非常な魅力を感じながら、1階の一番奥の部屋へ。やわらかな灯りの下、部屋のほとんどを占める大きなダイニングテーブル、たくさんの書物が載せられたピアノ、壁にかけれたギター、写真。ポスターなど、濃密な空気が漂っていますが工房はそこから続く隣の部屋、生活空間のいちばん端っこに付け足されたとでもいった感じに設けられています。工房でなかったら自転車置き場か何かになっていたのではないかと思えるほどのスペースに、必要なもの全てが収められている、つまり当たり前ですが、やはりこの場所であの美しいギターが造られているのだ、と思うと何とも不思議な興奮が胸に沸き起こってきました。ご子息の禰寝碧海さんは今回の取材が決まった時から「うちは本当に見せるべきものなんてないと思うんですよ、狭いし、乱雑ですし。」とよく仰っていたのと、禰寝氏と以前ほんのちょっとだけ無頼派の作家たちについて話したことなどを思い出し、その仕事場の生々しさについて勝手に頭の中で両者をつなげていたら、
「Orfeo の取材でフランスの製作家の工房を訪れた時、工房があまりに綺麗なので、本当にここでギターを造っているのか?と聞いたものだよ。ネヒメ(Alberto氏はこう発音しました)のはまさにギター製作者の工房だ」
とAlberto氏が仰った。それは尾野薫氏の取材の後に訪れた土田刃物店で彼が漏らした感想と通底するものだと思います。鋭敏な眼の感性を備えたカメラマンは空間やそこにあるものの自然な息吹を愛するのでしょう。

インタヴューは禰寝氏とAlberto氏とが直接スペイン語で対話する形で行われました。ギターを始めるきっかけ、スペインでのアントニオ・マリンとの日々、サントス・エルナンデス、ブーシェ、そしてフレドリッシュについて、木材についてなど。簡単なインタヴューですが禰寝氏のことを知らない海外の読者への、導入としては十分な内容。特にサントスについての話は、ギターに興味がある人にとってはとても面白い内容ではないかと思います。
そして撮影。空間というものをどのように切り取り、そしてそこに人物を配置する時どのように空間的な動きを生ぜしめるかなど、Orfeo Magazine で取り上げられてきた数々の工房の写真を思い出しながら、Alberto 氏はどのように撮影するのだろうと興味深く眺めてしまいます。禰寝氏の工房は先に書いたように濃密な生活空間と製作スペースである工房とがお互いに自己生成しながらまったくの独自の自然さで繋がってしまったようなところがあるので、つまり製作工房っぽく見せるのがとてつもなく難しい空間なのだと言えます。しかしAlberto氏は無駄なくてきぱきと撮影を進めてゆく。さすが、もうイメージは出来上がっているのでしょう。

取材が終わり、工房を辞す時も雨は降り続いていましたが、生々しいドキュメントに立ち会ったという高揚した気持ちが続いていました。雨の中傘もささずに車が出発するのを見送って下さった禰寝氏とご子息の碧海さん。アーティスティックとさえ言いたくなるほどの強烈な個性と作家性を持ちながらも、いつも礼節を重んじるそのお人柄に心を打たれてきたのですが、今回の取材を終えて、自分が作るわけでもないのに、「いい記事にしなければ」という使命感のようなものが湧いてきてしまいました。
考えてみればOrfeo magazine のNo.8 ではグラナダの製作家を特集しており、当然のことながら、彼の師であるアントニオ・マリン・モンテロが大きく取り上げられている。雑誌というメディアの中で、師と弟子が同じ地平に立つわけだ。二人のマエストロを紹介する誌面として、現在これ以上のものはないだろう。
そしてこの日の午後はそのまま車で次の取材へ。田邊雅啓氏の工房へと向かう。

「日本の製作家」特集 取材レポート 田邊雅啓 編
フランス、パリのCamino Verde社から出版されているクラシックギター専門誌<Orfeo>
いま世界中のクラシックギターファンから注目されるこの美しい本が、次号にて日本の製作家を特集する事が決定!!
この本の編集長であり、カメラマンとインタヴュアーも務めるAlberto Martinez 氏の取材に同行し、その現場をレポートするエッセイ。第3弾となる今回は田邊雅啓氏の工房 をご紹介。
製作家 田邊雅啓氏について語ろうとするとき、「現在国内若手製作家の中で間違いなくその先頭に立ち、次世代を担う俊秀」、という極めて月並みな讃辞の言葉がまずは浮かびはするのですが、それよりもまず彼の人間的な魅力の深さについて、それはもちろんギターという文化と音楽をこよなく愛するがゆえに特性として備わったものであるともいえるのですが、話さなければならない、という思いに駆られてしまいます。自身の仕事に誇りと責任を持ち、偉大な先人達へのリスペクトを忘れず(つまりいつも初心のみずみずしさと絶えざる探求心を同時に持ち続け)、寛容な厳しさと、さらには非常なユーモアの持ち主。かなりの碩学とさえいえるギターに関する広範な知識と認識の深さをも持ち合わせた方、とひとまずは(もっとたくさんありますが)言えると思います。実際に彼と会ったことのある方ならすぐに気づくことですが、ほとんど動物的な俊敏性とでも言いたくなる身振りの繊細な鋭さを持っており、手先が器用というのとは別次元で、彼の思考を完全に表現しうる指先の熟練を備えています。自身の積年の研究、求める最高の音、最高の形としてのギターという楽器を模索し続ける彼の作品は、そのどれもが必然的に「未完」のものでありながら、それゆえにどの個体も他にはない非常な魅力を持っています。
その終わることのない探求はどこへ向かうのか、という私たちにとっても興味深い問いに対する答え、とまではいかないまでも、図らずも今回のOrfeo Magazine 取材でその方向性を垣間見ることができたのは、それだけでとても貴重な内容だったと言えると思います。

前回の禰寝孝次郎氏の工房から、そのまま車で田邊氏の工房へ。東京から高速道路を乗り継いで午前に禰寝氏、午後に田邊氏の工房に、しかも取材同行という形で訪れることが出来るとは、ギター愛好家からすればなんという僥倖、と叫びたくもなるような出来事ですが、そんな興奮がOrfeo のスタッフに伝わったのか、
「あなたも一人一人の工房を訪れるなんて機会は今までになかったのではないかしら?これは素晴らしい経験だと思うわ」
とあっさり見透かされてしまった。まったくその通り!
田邊氏の工房は東京から高速で約2時間ほど。風景はやはり落ち着いており(高速道路わきの斜面に猪の親子がいた)、ただこちらの気持ちは禰寝氏の工房取材の興奮もまだ落ち着かない状態の中、到着。その日関東は広い範囲で大雨だったのですが、そういえば昨年秋の超大型の台風が何度も上陸した時に、大きな川が近くに流れる田邊氏の工房はギリギリのところまで浸水してきたというから驚いてしまった。実際に付近の方で甚大な被害を被った方もおられたことと察するほどに、田邊氏が無事で良かったと思わずにいられない。
田邊氏の工房は何年か前、NHKのBSプレミアムの「美の壺」(再放送はEテレでも放送)の「ギター」の回でご本人も出演して紹介されているので、ご覧になられた方も多いと思います。
工房の入り口で靴を脱ぐ、この日本独特の作法をもはや Alberto氏とOrfeoのスタッフは楽しんでさえおられるようだ。扉を入ってすぐのところが広い空間で製材スペースになっており、そこから8畳?ほどの応接間のようなスペース、そしてその奥に作業場がある。ざっと工房のなかをAlberto氏が見渡しスタッフと共に、「素晴らしいね」とひと言。まずは応接間でインタヴューが始まる(この応接間、田邊氏の書斎兼練習ルーム兼リスニングルームのような感じなのだが、その蔵書やCD、壁に貼られたポスターや写真など愛好家心をそそるものばかり。おまけに真空管式のアンプまであって、音楽を聴き込むということの主義を感じさせるところ、なんとも心地よい空間でした)。

「アウラで修理を担当するようになって、それまでになく様々なタイプの楽器を実地に検分し、研究する機会を持てたことはとても大きな、貴重な経験です。」
という田邊氏の答えに対し、
「君はスペインでロマニリョスに直接学ぶ機会を得て、他の名工達のエッセンスを汲みとって日本に帰ってきた。探求を重ね、アウラで世界中の多様なギターを研究し、そして現在の君があると思うのだが、その君がいまたどり着いたのはどんなギターなのだろう」
とAlberto氏が質問する、すると田邊氏は
「僕はやはりギターのエッセンスはトーレスだと思うんですよ。トーレスがもし生きていて新作を作ったとしたらきっとこういう音になるだろう、というのをイメージし、追い求めながら製作をしています」
と答える。これはAlberto氏からすると意外な言葉だったでしょう。おそらく彼は田邊氏の来歴とその言葉から(そのアーティスティックな姿勢から)、今こそ完全なオリジナルの音響を具現化せんとしているに違いないと予想し、質問を発したはず。
しかしトーレスこそがギターのエッセンスだと言い切るその潔さというか、到達点の純粋さと清冽な精神はやはり人の心を打たずにはおかないものがあると思います。

ここから更にトーレスの話になり、その特徴的な製作法のひとつとして、表と裏板の太い力木が先に構造材として横板に組み込まれていることを挙げると、Alberto氏はにわかに驚いた表情になり、
「それは初めて聞く話だ。とても興味深いね!そんな方法で作られたトーレスなど本当にあるのかい?ロマニリョスには話したかい?」
「話していません、僕がこのことを発見したのは彼のマスタークラスに参加した後ですから」
「話さない方がいい、彼にぶん殴られるぞ(笑)」
「確かOrfeo Magazine に掲載されていた製作家でも、同じ工法を踏襲していると思われる方がいたはずです。」
(※この話は確かに非常に興味深く、田邊氏は彼なりの知見でなぜトーレスがそのような工法を採用し、それによってどのような音響的な効果が得られるかなどもある程度まで認識をされておられるようだ。これはまた別に機会に、じっくり彼に聞いてみたいと思う)
工房の撮影に移り、床にはその日の午前中の作業でできたばかりの木くずが生々しく残っているのを見て、撮影に集中する厳しい表情ながらもやはりAlberto氏は何だか嬉しそうだ。禰寝氏の工房で話してくれた、撮影前にやたらに工房を整然と綺麗にしておくヨーロッパの製作家とは違って、この作業の場が持つ雰囲気を愛するのだろう。とはいっても田邊氏の工房はただ雑然としているのとは全く違う、かれの美意識が自然に通底した空間になっているのが何とも独特の心地よさを生んでいる。彼は壁にマスキングテープで貼られたモザイクの薄い破片や、工具の配置、横板固定器にも被写体としての興味を示したのかシャッターを切っていく。

写真というのは事物を異化する不思議な力があり、というよりその被写体の本質を我々の肉眼が可能な以上に映像として物質化することができるので(もちろんそれは優れた写真家にしか出来ないことなのですが)、この工房の一つ一つのモノたちの佇まいがどのように表象されるのかが本当に楽しみなのですが、それにしてもこの工房で撮影された製作家のポートレート(特集ページの扉となる写真)は田邊雅啓という人の個性と本質とを余すところなく表現し、秀逸なものだと感嘆せざるを得ない。
田邊氏は今回の取材が決まるずっと以前からOrfeo Magazineを購入して熟読しており、筆者同様にその内容の密度とエディトリアルの美しさに賞賛を隠すことがなかった方で、当然ずっと取材を楽しみにしてこられた。想像していた通りというかそれ以上にギターに詳しく、ギターを愛し、そしてその美しさを写真として具現化する名カメラマンにしてエディターのAlberto氏と過ごした時間は、田邊氏にとって本当に貴重で幸福なものだったに違いない。

「君のギターへの情熱と探求心は素晴らしい。ぜひこれからも良いギター作り続けてくれ。」
取材を終え、工房を辞す時にAlberto氏が心のこもった激励の言葉を送る。
Alberto氏に取材同行した女性(実は彼の奥様でCamino Verdeの編集者)へ、田邊氏は日本の美しい手ぬぐいをプレゼント。日本の文化に少なからず興味を持っているらしいこの素敵な女性に、これは最高に気が利いた贈り物だろう。彼はこういうことが出来る人なのだ、つまり紳士的なスピリットが自然に備わっているのである。最初に戻るが田邊氏を語ろうとするとき、やはりこのことに言及せずにはおれないのである。

高速道路で帰路に就く、途中のサービスエリアでスタバに入り、みなカプチーノを注文する。すっかり同じ空気だ。

「日本の製作家」特集 取材レポート 栗山大輔編
実は今回の取材の正式なオファーがAlberto 氏とCamino Verde のスタッフからあった際、取り上げる予定だったのはアルベルト・ネジメ・オーノ(禰寝孝次郎)、尾野薫、田邊雅啓の3人だけでした。Alberto氏は当初、彼がこれまで<Orfeo>で取り上げてきた製作家達と同様に、ギターという楽器における同じdistribution systemのなかで彼ら3人が製作をしていると思っていたはずである。つまり生産者(製作家)から仲介者(店舗)、そして受け取る人(カスタマー)という到って普通の構造の中で、ひたすら生産に特化して従事する職人としての製作家を考えていたのだと思います。
しかしながら製作家達のその作業はしばしば孤高の様相を呈してしまいがちであるし、それゆえに個性的なものが生まれたりもするのですが、日本のような国で単発的な個性だけが花開いて消えてゆくのでは、文化として根付き、その後に続く大きな流れを形成するには至らないままになってしまうのではないだろうか。
私達Guitarshop AURA が、積極的にその役割を担おうとしてきたことの一つは、この日本に本物のギター製作文化を根付かせることであるとも言えます。そしてそこではそれぞれの作家的特質を維持しながらも、自然に建設的な議論が起こり、あるべき音とは何かという、至極まっとうな探求へと皆がつながってゆくこと。そしてこの議論を閉じたものにせず、カスタマーさえも巻き込んでいきながら、ささやかだけどもとても強い意志の場をあくまでショップとしての立場でAURAが提供していること。つまりあくまでそれは民主的であり、ショップとしてのカラーで統率するようなことだけは慎重に避けてきました。
Alberto 氏と取材に同行しながらギターについての様々の議論やお互いの情報交換を重ねてゆくうち、ショップという販売の場が単なる distribution system の一要素としてではなく、上記のように「作ること」、「議論すること」、「育てること」などを通してのコミュニティを形成するアクチュアルな現場として機能していることに、氏は非常に関心を持つようになりました。
前置きが長くなりましたが、今回ご紹介する栗山大輔、清水優一、禰寝碧海の3人の取材は来日滞在中に急遽決定しました。日本における本格的な伝統工法浸透の嚆矢となった禰寝孝次郎や尾野薫、この時点で彼らの取材を終えていたAlberto氏は、彼らを受け継ぐものたちとして、そして彼らの造る楽器の完成度の高さゆえに、自然に興味を抱くに到ったのです。

フットワークが軽く、何事においても速く、好奇心旺盛で、それでいて決して過剰にならない栗山氏は、見ていていつも「充実」という言葉が浮かぶひとです。それは彼が製作したギターを見てももちろん感じることで、一切の妥協のない精緻な仕上がりながら、一気に無理なく完成したかのような、まるで最高の手練の画家によって短時間で仕上げられた油彩画を見るような感覚にさせられるのです。
東京郊外の栗山氏の工房は、瀟洒な一軒家の中の、1階の6畳ほどの一間を改造して使った空間。物が生まれる場所がしばしば持つむせかえるような生々しさよりも、作業現場らしいある程度自由な配置の中に心地よい統制があり、なんとも心地よい空間になっています。
Alberto氏は撮影をしながら質問を続けてゆく。栗山氏に自作のギターを抱えさせ、ポーズを取っているところを撮影するのだが、栗山氏が珍しく表情が硬い、なんとどうやら緊張しているらしいのだ。

「さあ、何か彼に話しかけてあげて(笑)」とAlberto 氏が私に言う。何しろメディアの最前線で仕事をしてきた超一流のカメラマンなのだから、表情が不自然になっていることなどファインダーを通した彼の眼はすぐに見抜いてしまう。私がまったく関係のない話題で単純に普段通りの会話を栗山氏としてみる、慣れてきたところで自然に出てきた笑顔が見事に捉えられ、今回の誌面に使われた。
この工房を訪れたとき、ちょうど進行していたひとつのプロジェクト「6人の製作家×KEBONY Guitar」のまさに本体が栗山氏の工房にあったのである。これは今回Orfeo Magazineで取り上げられた6人の製作家が、アルベルト・ネジメ氏の総合監修のもと工程を分担して1本のギターをつくり上げるという世界的にも前例の思いつかないプロジェクトであり。この時は栗山氏が工程を担当しているところだったのです。(※Kebonyという新開発の木材については別の記事で詳しく述べているのでそちらをご参照ください)

その話を聞きそしてその実物を見たAlberto 氏はやはり興味を惹かれたようで、製作途中のそのギターも撮影。木材そのものにももちろん注目していましたが、やはりその製作背景に強く関心を持っていました。この文章の冒頭でも述べましたが、単なる師匠と弟子というだけでなく、individual な個の有機的な集まりとしての彼らのあり方と、それが一つの楽器として結実することの稀有を、Alberto氏は認識しておられるようでした。

「日本の製作家」特集 取材レポート 清水優一編
栗山工房からそのまま清水優一工房へ向かう。
清水氏ほど実直に、自身が師と認めた人の製作哲学と技術を学び、それをできる限り理解しようと努力を惜しまず、どんなに時間をかけようとも実践し自らの感性の中に着地させてきた製作家というのも、なかなかいないのではないだろうか。もちろん他の製作家が不誠実であるとかいうことはなく、清水氏の場合はその集中の濃度が異様に濃いのである。そして生まれてきた楽器の言葉で説明しようのないある種の密度は、毎回異なる個性を放ちながら、着々と何かの核心に向かっていることを感じさせる、非常な魅力にあふれている。
人柄もまた真面目で、店頭でリペアを担当している時に彼に接したことのある人なら、その生真面目で温厚な話しぶりに深い印象を持つと思う。さらに重要なのは、そのような実直さと同時に、おそらく彼自身がまったく意図しないところで生まれる天性の自由さがあるということでしょう。この「自由さ」が今後彼の製作するモデルにどのように立ち現われてくるのかが楽しみでならない。
清水氏の工房は実家の離れの日本家屋を改造したもので十分な広さがあるが、ここまで訪れた工房がどれもそうであるように、無意味な余白がなく、製作家の意思が行き届いている感覚がある。
通訳を使わず、片言ではあるが自分自身で英語でAlberto 氏のインタビューに応えてゆく。河野ギター研究所で10年以上もの間従事したあと、尾野薫氏との出会いによって自身の方向性を確信するくだりは、簡単に語られてはいるが感慨深い。現在制作中のロマニリョスモデルとハウザーモデルの表面板の工作精度をじっくりと見つめ、撮影したあとにAlberto氏は彼に激励を送っていた。


そしてこんな会話も
「年間何本製作しているんだい?」とAlberto 氏。
「多くて5本くらいでしょうか」
「君は若くて、これからもっと学ぶことがあるし、君の楽器を求めている人もたくさんいるはずだ。(ダニエル・)フレドリッシュは駆け出しの頃、とにかく作りまくって年間何十本と仕上げていたそうだよ(笑)。君自身と君の楽器を求めている人のために、もっとたくさん作るべきだよ」
「日本の製作家」特集 取材レポート 禰寝碧海編
碧海氏は数年前まで父孝次郎氏の工房でともに製作をしていましたが、現在は都内に独立した工房を設立し、精力的に製作を行っています。
偉大なるマエストロ、グラナダの名工アントニオ・マリンの工房で直にスペインの伝統工法を学び、呼吸するようにそれを体得して帰国した彼の製作に対する姿勢は、彼にとってあるべき音に対する探求と実践とで一貫しています。伝統工法へのリスペクトは誰よりも深く、それゆえにこそ彼は彼の考える理想の音響に対して貪欲で、真剣に悩み、そして答えを出してきました。その一つ一つの異なる答えとしてのギターの、素晴らしい美しさに、彼の師匠でさえ感嘆するのです。それでも彼はすぐに次に出すべき答えを模索します。碧海氏には本当に申し訳ないが、作り手がその創造の過程において苦闘するのを見るのは、実は私のような受け手としては非常にわくわくさせられることでもある。次はどんなギターになるのだろう?
Alberto氏の今回の取材に同行して気付いたのは、とにかくAlberto氏の情報収集の正確さとその量で、その取材に対する誠実な姿勢に特に感銘を受けたのを筆者は記憶しています。碧海氏についてももちろん仔細にデータを収集していたのですが、Alberto氏は彼がダニエル・フレドリッシュモデルをラインナップしていること、そして写真で確認できる限りですが、その工作精度の高さに興味を持っていたらしいのです。
Orfeo magazine の過去の記事でも1号まるごとをフレドリッシュで特集してしまったこともあるし、なによりも個人的にも友人関係だというAlberto氏だけに、興味を持つのは当然だったのでしょう。アントニオ・マリンに薫陶を受けた碧海氏が、オリジナルモデルともうひとつメインにしているのがフレドリッシュモデル。そして詳しくはここでは述べませんが、フレドリッシュのコピーモデルを作るのは非常に難しく、そして製作家として大きな覚悟のいることなのです。もちろんそれは、Alberto 氏もよく分かっているのでしょう。
そんな彼にAlberto氏は工房にて驚くべきプレゼントをする。なんと今回の来日に際し、彼ははフレドリッシュ本人がストックしていた(もちろん自身のギター用として)、表面板用の杉材を碧海氏のために持参していたのだ。巨匠からの直の贈りものを、フレドリッシュモデルを製作する若き職人に手渡した時の感慨と意味の深さは、その場にいる誰もが感じたはずである。
この貴重な材を、碧海氏はいつ使うのだろうか。何とも楽しみな仕掛けを、Alberto氏は置いていってくれたものだ。

No.15 特集「日本の製作家」が掲載されたオルフェオ・マガジン合冊号(11-15)のご購入は、